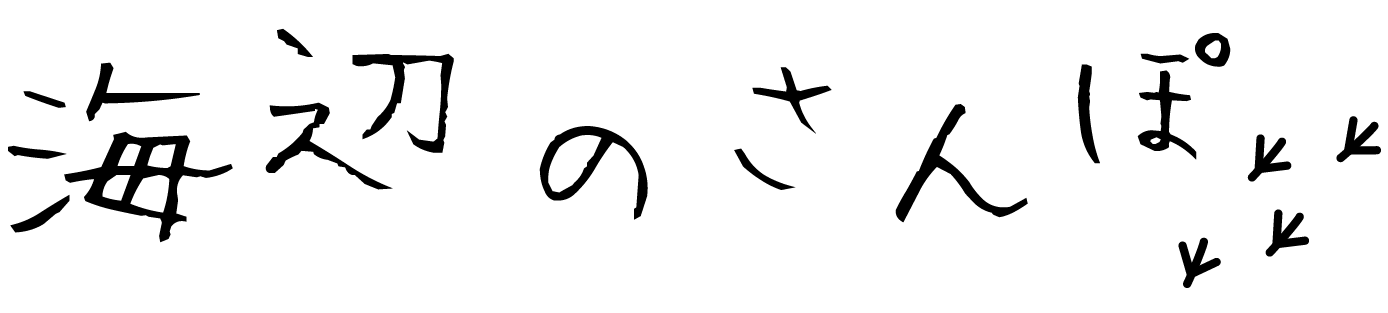夜光貝 Sea shell
概要
ヤコウガイ(学名 Tarbo marmoratus )
リュウテンサザエ科最大種。とても大きくなるが成長が遅い(稚貝から3年で約7cm)
インド太平洋の温暖なサンゴ礁海域に生息する。日本では鹿児島県の屋久島が分布北限
名称
7世紀以前のヤク地方(現在の琉球弧)でとれる貝という意味のヤクガイから。9世紀以降の文献では屋久貝とも表記される為、分布北限の屋久島に因むとの説もあるが、遺跡での出土状況を鑑みると屋久貝が当て字の可能性が考えられる。
人との関わり
沖縄先史時代より食用にされてきた。弥生時代頃の奄美大島と久米島を中心に遺跡で大量の殻が発見され、古代より交易品として需要があったと考えられている。8世紀頃始まる本州の螺鈿細工との関係が注目されている。
琉球王朝時代は「貝摺奉行所」があり、螺鈿の材料として夜光貝の加工が国家事業として行われていた。
貝殻
炭酸カルシウムを主成分とし、結晶構造の隙間をたんぱく質が埋めている。茶色の殻皮の下に外側から緑~白の方解石層(カルサイト)、内側に真珠層(アラゴナイト)の配置で構成される。夜光貝の真珠層は結晶の密度が高く、最も頑丈と言われている。
骨 Bone
ボーンカービングの材料として牛の大腿骨や鯨の顎骨が有名だが、他に代表的なものとして水牛や鹿等の角、鯨や象等の大型哺乳類の牙があげられる。
沖縄では縄文時代にジュゴンの骨を加工した美しい装飾品が作られていた。「蝶型骨器」と呼ばれる複雑極まる造形の装飾品は、位の高いシャーマンが着用したと考えられている。ジュゴンは進化の過程で浮力調節の為に骨の密度が高くなっており、頑丈なアクセサリーが作れたと考えられる。
ハワイ島では遺跡から人骨製の釣り針が多く見つかっているが、タヒチでは人骨は使われず全て貝製である。資源の乏しい島嶼環境で生きてきた先人の工夫や島毎の考え方の違いが垣間見える。考古学では土器の形態や模様によって年代を推定する「形式編年」という手法があるが、ポリネシアには土器が少なく、代わりに釣り針の形態を用いた形式編年が行われた。
木 Wood